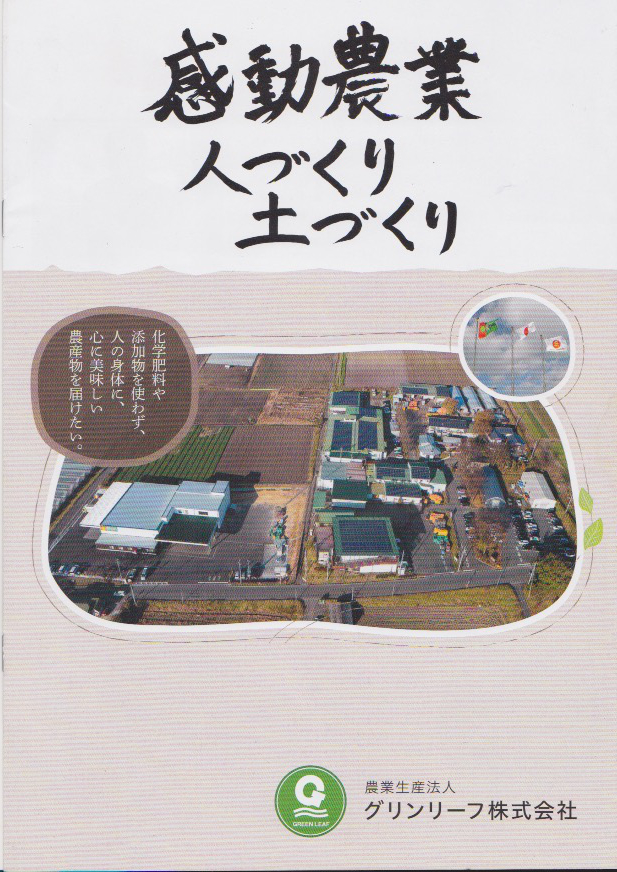果たして伐根直径80センチ前後の大径木が無事に倒れました。ポイントとしていた伐り株を越えず、望んでいたラインに落ち着いてくれました。これでじっくり乾燥させることができるし、搬出もごとごと安全に行えます。


必要な道具を揃え、ラインを定めるのに三週間を要しました。体力の回復を待つ必要もありました。とはいえ、プレッシャーが長引くのはしんどいものです。集中力がここぞという時に発揮できず判断が鈍るかもしれない。とはいえ、その間、検証を重ねることができました。前日まで二日つづいて風が強く更に足踏みすることになりましたが、結果的にはそれも良かった。改めて現場を整えつついろんな角度から見直し、最後は滑車を取り付ける立木を変更するに至りました。
今一度今回の仕事を振り返ってみる。
前回同様、難しいのは倒れて着地したラインが最終ラインではなく目標ラインでもないことです。現場は上を通る道にカーブミラーがあるように、直線的に続く斜面ではありません。そしてライン手前が大きく落ち窪んで谷のようになっています。だからそのまま横方向に倒しても円に描き入れる接線のように土地に沿わず、また谷へ渡すようになります。下方に設けたラインは比較的カーブが穏やかであり、谷はこれまでに伐った竹や木で埋めてあります。
倒れてからの動きをイメージする。まずはじめに木の先端である梢が着地する。立木と立木の間にがっちり噛み込んで固定されれば、そこを支点として、扇が開くように元口から樹幹は谷側へ動き、ポイントとしている伐り株で止まり、目標ラインに落ち着く。前回のように予想以上の力で跳ね上がることのないよう、角切りをしておきます。ライン手前に高く残してある竹の伐り株がクッションになってくれることを期待。いずれにせよ、ツルは衝撃で引き千切れるでしょう。
最終決定したラインをメージャーで測る。滑車を取り付ける立木まで約15メートル。手前の伐り株に激突せず、寝かしてある木の元口付近をクッションに、そして奥にはもうひとつ伐り株がライン下方、目標ラインとの間にあったので斜めに切り下げておきました。

さらに引いて、下を通る道から。樹高は20メートルをゆうに超えるでしょうから、梢が道に被さることになります。写真上は当日、牽引具をセットしたところ。中央が倒す木。その右隣に滑車が取り付けてあります。その木と倒す木を挟んで左隣にある立木との間に倒す。左、谷側にそれると、水平ラインを交差し、梢が意図せぬ具合に引っかかって強い緊張を生む。山側へそれても厄介です。樹幹が斜面上に不安定な形で止まり新たな危険を生む。ここが何となくだと、本番作業中、肝心の受け口が定まらず常に漠然とした不安を抱え続けることになります。
写真の真正面に倒したい。両側にある立ち木の真ん中ではなく、滑車を取り付けた山側よりであることがポイントです。樹幹はわずかに谷側へ曲がりまた山側へ直ろうとしています。重心は若干谷よりだと思うので、伐倒ラインを意識的に谷側へ寄せることはしません。
写真下、反対から見る。ありがたいことに滑車を取り付けてある牽引ライン正面の木も梢が山側へ反っているから、ギリギリを狙ってもうまく避けてくれるでしょう。


 最後に木の下に立って伐倒方向を確認する。
最後に木の下に立って伐倒方向を確認する。
かつて経験したことのないサイズ。60センチをゆうに超えるだろうくらいに思っていましたが、事前にチェーンソーを持って、どう切るか足場の確認も含めて木に当ててみて目を疑う。バーの倍近くかそれ以上あります。胴回りを測ってみると2メートル40センチ以上。受け口のラインだともっとあります。直径×3.14=円周に当てはめれば79センチ前後と出ました。否が応でも重圧がのし掛かります。
足場は竹の伐り株とその間に木を渡した簡素なもの。受け口も追い口も谷側から正対できません。どうするか。朝までじっくり布団の中で考えます。正対できなければ突っ込み切りはできない。チェーンソーの特性を思い出して、一番無理のない方法をあれこれ考えます。本を読んで答えを探そうかとも思ったけれどやめました。
当日は風が止みとても静か。牽引具のセッティングも順調にできました。改めて、今回ぬかってはならないポイントを思い出す。受け口の下切りの角を欠くこと、そして芯を入念に切っておくこと。一息入れてから伐り始めました。思っていた以上に受け口の調整が難しい。谷側からだと胸よりも高い位置にあり、チェーンソーを逆さに構えて山側からのラインに一致させるのは至難の業です。目で確認しながら進めることさえできません。なので手鋸とヨキ、そして山側から回りこんでチェーンソーの切っ先で調整しました。手鋸はいつも使っているものは寸足らずなので、錆び付いていた伐採用であろう年代ものを事前に目立てしておきました。それなりに切れるようにしたつもりが思うように切れない。アサリの具合が甘いのか。しかし試し切りした時はこんなではなかった、、、何か不安が残ります。
深さ20センチで一旦うまく作れました。もう良しとしたいところ、思い直して25センチまで深くしました。根張りの絡みでツルの強度に心配が残るからです。水準器を使って水平を確認します。規模が大きくなればなるほど、ちょっとした誤差が大きなミスに繋がります。
追い口についても水準器を使って目印をつけ、いざ、刃を入れ始めました。感覚による水平と目印のと間に誤差はなく順調に進んでいます。が、途中であろうことかソーチェーンが音をたてて切れてしまいました。はじめてのことに目が点になる。どこからどこまでを切ったところかというと、写真下の伐り株に追い口谷側から手前に向けて斜めにバーの形が連続するように跡がついているところ。まだ半分も切れていません。現場を離れるわけにはいかないので、あとは鋸でやるしかありません。目立てをしておいて正解と言いたいところですが、替え刃を用意していなかったにがそもそも甘い。嫁におにぎりを頼みました。
体力が急激に消耗していきます。生きていると木はこれほどまでに違うものか。まるで切られたそばからその傷を治そうとするように体液が滲み出し肉が盛り上がり、まるで鋸が取り込まれるようです。引くにも押すにも力がいる。しかし、力任せにしてはいけない。今一度気を引き締めなければ。とはいえふらふらです。寸足らずの鋸である故に思うようにいきません。谷側から山側から切り込んでいきますが、中心付近が切れ残り、直線にすべき追い口のラインがハの字になります。そんな状態で無理をして楔を打つのは好ましくない。
楔はチェーンソーによる切り口に打ち込む想定だから鋸による切り口そのままでは狭くて入りません。追い口の真正面一個と谷側に一個の二つではじめる。途端に谷側の楔が割れた。替えを打ち込み、少し持ち上がってきてから山側を入れる。これで楔が三つ。と、今度は、真ん中の楔を打ち込んでいる木口が裂け上がりはじめた。根張りだからなのか、はじめてのことでわかりませんが奥の方は大丈夫そうだし楔は順調に入ります。次から次へと思わぬことが続きます。深呼吸をして下腹に力を込める。新しい楔を2つ追加。追い口を切り進めつつ、合計5つの楔で打ち進め、牽引具で追いかける。決して、牽引具の力で強引に倒そうとしてはならない。
明らかに谷側が重い。比較的厚めに残していた山側のツルが先に音を立てた。いよいよ重心が谷側にあることは明確です。谷側のツルを重点的に切り進め、楔を打つ。まだ裂ける音はしません。一連の作業を繰り返す。ようやく谷側が鳴った。山側も追いつく程度に進めます。
本格的に裂ける音がして倒れ始めるまではあっという間でした。かかった枝もなんのその、自重で折って折られて倒れました。圧倒的な量感でした。恐ろしさの余韻はなかなか消えません。
実は作業途中、チェーンが切れたあたりから地域のお歴々が観にきていたのです。この手のプレッシャーには大丈夫になりました。楽しそうにしてくれているのがこちらも嬉しい。無事に倒れたことを見届け、しばらくお喋りをしました。明るくなったことを喜んでくれているようです。色々話を聞かせてくれました。やはり、集落に藪が迫っているのは火事のこともあって不安に思っているそうです。そして、こういった太い木ほどプロに頼んでも伐ってもらえないとのこと。つまり、業者からすれば、藪を片づける余計な手間がかかるわりに、虫食いや腐れなど、材としてお金になるかどうか確証が持てなかったり、集落の中にあってリスクが高かったり、割に合わないから請け負えないということなのでしょう。どうしようもなくそのままになっている現状を不安に感じているのは同じだったのです。
小学生の時、倒木更新という言葉を国語の授業で習いました。寿命尽きた木が倒れ、新たな芽を育むという話です。何故伐るのか。まず大前提として、木もまた永遠ではないということです。木は人を生かしもすれば殺しもします。
 改めて、受け口の正面を二等辺三角形を使って確認する。ゲートとした立木の間、山側ぎりぎりを狙えていた。
改めて、受け口の正面を二等辺三角形を使って確認する。ゲートとした立木の間、山側ぎりぎりを狙えていた。
 狙ったところに着地後、樹幹が谷側へ落ちるに従い梢先端は、写真中央から山側へ角度を変えた。
狙ったところに着地後、樹幹が谷側へ落ちるに従い梢先端は、写真中央から山側へ角度を変えた。


伐倒方向の直径は85センチ。
受け口の深さは24~25センチ。(基本は直径の4分の1以上、大径木の場合は3分の1以上とされる)受け口の深さはツルの強度、追い口に楔を打ち込む奥行きを考えて決める。
ツルの幅は谷側が10~15センチ、山側が17~18センチ。(基本は直径の10%とされる)今回は斜面横方向に倒すので基本より強度がいる。十分な厚さから調整を進めた結果。
ツルの高さは17~18センチ。(基本は直径の15%~20%とされる)今回は少しでも倒れる勢いを緩めるため、ツルに粘りを持たせるため、高めに設定した。
側方から測った直径は71センチ。


何故チェーンが切れたのか、改めて問うて、はたと思い出す。受け口を入れ始めた時から妙に切れないおかしいとは感じていたのです。何か金属にあたっているような、刃が滑って食い込みが悪いような。異音が混じっているようにも感じました。しかし、明確な原因が浮かばなかったので作業を続けました。
一晩経って思い至る。デプスゲージの調整が甘かったのではないか。デプスゲージとは名前の通り、刃が木に食い込む深さを調整するもの。大工さんがカンナの刃を金槌を使って台木からの出具合を見るそれです。前日の目立てで確認をしてはいたのですが、自分の認識が甘かったようです。燃料満タン1回分ほど使って、最後の方は若干切れ味が落ちた感はあったものの特に違和感はありませんでした。そして当日、念のため再度目立てをしたことで、気づかぬ程度だったのが決定的になってしまったのでしょう。これまで時々削って下げたことはあったものの、さほど必要性を感じていなかったので、勝手にバランスは取れるもので敢えて調整する必要はないのかなくらいに思っていました。
 左右の刃が交互に連結してるソーチェーン。1箇所だけ同じ側が続くのだが、そのところが切れた。
左右の刃が交互に連結してるソーチェーン。1箇所だけ同じ側が続くのだが、そのところが切れた。
 追い口を切るときに出た切り屑。それほど悪くはないがよくはない。
追い口を切るときに出た切り屑。それほど悪くはないがよくはない。
 受け口の切り屑は繊維に対して斜めに入るので粉っぽくなる。ちなみに、繊維に対して平行に入れると下の写真のように切り屑は長くなる。前日、樫で予備の楔を作る際に出たものだ。この時点ではさほど悪くはないと思ったのだが。
受け口の切り屑は繊維に対して斜めに入るので粉っぽくなる。ちなみに、繊維に対して平行に入れると下の写真のように切り屑は長くなる。前日、樫で予備の楔を作る際に出たものだ。この時点ではさほど悪くはないと思ったのだが。
あるいは、チェーンを張りすぎたのか。いずれにせよ、今後、気をつけるいい経験になりました。