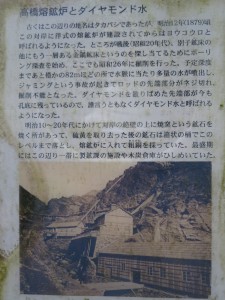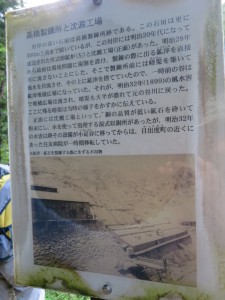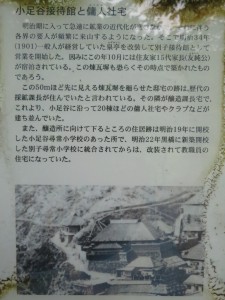3年かかった畑西側の伐採一番の難所が終わりました。この最後の一本を伐る為に、これまで時間を掛けて組上げてきた仕事の全てがあったと言えます。



牛舎脇に立っていた直径60センチ弱の杉。倒す方向が電柱を支えるワイヤーによってさらに限定されていました。なによりも牛舎や電柱、電線に倒れないようにするため、その対角にあるワイヤーが張られた方に倒すことができたなら、あえて危険を冒す必要もなかったのですが、手前に設けられたウォータースライダーのような水路といい、事故を誘発する要素が重なっています。さらに、今回は倒す方向にロープを引っ張るための立ち木はありません。薮に呑まれ朽ちていたのです。さすがにこれは無理かもしれないと思いました。
しかし、諦めてしまうと状況は悪いまま。その覆い被さる木によって、この先もずっと畑の空気は淀み、露に打たれて作物はじわじわ傷み、どう仕様もない気持ちに重く暗く沈む自分を思うと、やるしかない。大げさに聞こえるかもしれませんが、そもそも耕作放棄されていた土地なのです。まわりも手入れをされずひどい状態でした。薮蚊も多く居心地の悪いところで元気な作物が穫れるわけもなく、そこに通うのは苦痛。私が借りているのは手前の畑で、奥の薮を手入れすべき責任はないのですが、地権者に掛け合って伐らせてもらうことにしたのです。しかし、最後の一本はクセが強く大径木であることに加えて、電線や民家(牛舎)の際に生えているという更に困難な状況にあったため、確実に安全に倒せる保障はありませんでした。
周りの竹を取り除き視界が広がって行くと、一筋、いけるのではないかと思える方向が見えてきました。さらに数日かけて考え、眠れない夜はじっくり布団の中でイメージを深めました。体力の回復を待ち、気持ちを固めました。
まず、電線と牛舎側に張っていた枝を届く範囲で落とし、斜めに張られたワイヤーをガードするよう、そばに生えていた木を高い位置で伐り倒しておきました。基礎に立ち上げられたブロック壁(牛舎壁の一段下、一枚目の写真で私が歩いている所)にもあたらないようにと考えると倒せる方向は本当に一筋しかありません。そして、倒れる際にどういう動きをするか、着地してからワイヤーの方に転がってしまったり、跳ねた樹幹がブロック壁を壊したりしないか。しかし、倒れるときは、これまでの伐採で3メートルに積み上がり斜面に張り出した竹の足場を支点として樹幹は持ち上がりつつ前方へスライドし、ブロック壁もワイヤーも越すはずなので、いけると思ったのです。隣に生えていた細い木で実証もできました。念のため、ブロック壁上面には笹の束や竹の枝葉を厚く敷きました。
チェーンソーのバーは幅40センチ。木の直径よりも短いので、切り進めるには反対の斜面下側に回り込む必要があり、切り口が胸高より上になってしまいます。危険な作業になり水平に切り進める事も難しくなります。そこで本来ならば足場を組むために段取り、まわりの竹もそれを踏まえて伐り進めていくのですが、ひとの土地ということがあって思うようにいきません。大詰めにさしあたって残していたのがいつの間にか無造作に伐られてしまっており、その株に足を掛けての不安定な作業になってしまいました。
何度も向きを確認しながら受け口を定める。芯切りの際に腐れが入っている事が分かりました。その範囲が定かではないので幅を控え、「つる」を厚めに残すようにする。条件は万全ではなかったものの、一つひとつ確認しながら作業を丁寧に進めました。
しかし、楔(くさび)を打ち始めたところで吹いた少しの風。木を見上げれば恐ろしいほどしなり、あろうことか、最も避けるべき方向に傾こうとしたのです。薮を避けるよう山側に反っていた木が、倒す方向に少し傾いたことで牛舎に向かって反る形になったのです。血の気が引くとはこのことか。
一巻の終わりかと泣きそうになりながら、牛舎に倒れないよう必死に何度も何度も楔を打つのですが、思うようにいかない。急がなければ、、、蝶番(ちょうつがい)であるつるがもげれば終わりだ。しかし、もげないよう、厚く残していたことがかえって、楔を入れにくくしていました。次の一手をどうするか、「やるべきこと」と「やってはならないこと」、そして手順の一つでも掛け違えてはらない。民家に隣接しない山の中なら躊躇せずにやってしまえることが、ここではどうしてもためらわれます。次にやるべきことがそれなのか、確信がなければできません。
つるが厚過ぎることもまた危険であると手引書には書いてありましたが、では具体的にその機能においてどういう結果を招くから危険なのか、経験がないので分かりません。しかし、これまで同じくらいの厚さで直径50センチを超す木は無事に倒れてきました。楔が少しずつでも入るならば先ずしっかり入れるべきだとは思うものの、無理が過ぎればつるはもげるかもしれないという不安も拭えません。とにかく、少しでも入りやすいように、ロープで引っ張ることにしました。支柱とする立木は竹しかありませんが連結させて強度を持たせるしか、仕方がありません。伐り始めた木の下を行ったり来たりすることが絶対に危険なのはわかりますが、牛舎ばかりか、まさか家屋に倒れるなんて許されるわけもなく、嫁や家族には申し訳ないけれど、その時の私には、たとえ木の下敷きになっても仕方がない、自分が死んで詫びるしかないという思いがよぎっており、とにかく克服するために必死でした。無事に済んだとお疲れの乾杯をしたい、その一念に集中しました。
予め水に浸しておいたにもかかわらず、ヨキ(楔を打つ手斧)の柄が半ば折れて抜けてしまいました。代わりを取りに家に駆け戻り、ロープを張るために斜面を登って降りて、、、その間も風が吹き付けます。抜きようのない力みから、急速に体力を奪われ、息があがり、喉が乾き、しゃりバテの予兆も見えてきました。水を呑み、嫁が用意してくれていたおにぎりにかぶりつき、チョコレートをむさぼり食いました。最悪の事態を考え、牛舎に声を掛けに行きました。しかし、留守。
つるを調整しなおす場合は、追い口をさらに切り込むよりも、まず受け口を切り直すほうが先だと念頭にありました。今回は楔だけで倒す事が前提だったので、追い口が充分に深くなければならないと考え、対する受け口を浅めにしていたのです。これはあくまで私の解釈ですが、つるの位置が木の中心線よりも前にありすぎることは、例えば、取り付ける二つの蝶番を両側に離すべきところ、寄せすぎて結果ぐらつきやすくなるというように、横方向の力に対して極端に弱くなるはずなのです。つまり、楔が効かないからといって受け口をそのままに追い口を切り込むことは、つるを薄くするだけでなく更に前へ動かしてしまうことになり、牛舎に向かって吹く風に対して絶対に弱くなる、この状況でもっとも「やってはならないこと」の一つのはずなのです。
今回の経験で確信を深めたことは、やはり「受け口」が倒す方向を決める「起点」であるということ。一本一本条件の異なる木を倒したい方向に倒す行為においては、不確定な要素やわからないことが依然としてあります。しかし、ひとつひとつの手段においては、起点を拠りどころとして定めなければ、後で微調整をくわえることも、論理的に組み立てることもできなくなる。すべて漠然としていては、この失敗の許されない状況において次の一手を打つことができないと思い知らされたのです。なので、切り直すときは向きが変わらないよう細心の注意を払いました。反対の斜面下側は足場が定まらないので繊細な作業ができない。直線を出すのがとても難しい作業になりますが、片側からバーの先端部でほんの少しずつ、目で確認できる幅だけを均等に切り進めるようにしました。少しでも傾いたタイミングを見過ごすとバーが挟まって抜けなくなります。その時点でさえ倒れていなかったら、確実性をもって駒を詰めることは、もはや不可能になります。切り残しはヨキで慎重にはつりました。しかし、木は反応しません。既に、楔を追い口に埋まるほど打ち込んでいます。時折吹く風がいやがおうもなく緊張を強います。時間がありません。日も暮れ始めています。
残るは追い口に手を加えるしかありません。深く設定していたおかげで、なお手のこが入る隙間がありました。手引書にかかれていた偏重木の伐り方、追い口を受け口に平行ではなく少し角度をつけて入れる、という方法は頭にあったものの、今回の状況に確信を持って当てはめることができずにいました。しかし、もはやその一手を入れるしかありません。谷側、真ん中、山側と3つある楔を打ち込むときにうける抵抗の違いからも木の重心が山側(牛舎側)にあることは明らかで、意図せず打ち進めれば、先に谷側のつるから裂け始めて山側に倒れてしまうところ、より強く打ち込んでいた山側にだけ入っていました。思うように楔が効き始めている証拠です。風に耐え、最後までもってほしい谷側のつるはそのままに、山側にだけ少し切り込みを入れて楔からの圧力に耐えている力を開放する、今こそ、その目的が、手引書に書かれていた方法と一致する、そう確信しました。
日も暮れてぎりぎりのところ、なんとか間に合いました。結果は一枚目の写真で分かるように、無事に障害物を飛び越え、牛舎にも電柱や電線にも触れることなく倒すことができました。最後の一手を入れ、即座に木が反応して音を立てたとき、「これで牛舎には倒れない」、選択が間違いではなかったことが分かり、かく汗に温度が戻ったようでした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
私は林業に携わった経験があるわけではなく、今回の伐採は明らかに身の丈を越えていました。思い返しても冷や汗が出ます。しかし、やるしかなかった。
このような支障木はやっかいだからこそ、これまで放置されてきたはずです。本来ならば電線を張るときや水路をコールゲートにするときに伐り倒しておくべきだったのでしょうが、ではその時、だれがお金を払い、だれがリスクを負うのか。問題となった一本を伐り倒すためには、事前に竹藪を一掃し、作業ができるように後始末をつけておく必要があるはずです。安全を確保するためには重機を使う大掛かりな仕事になるかもしれません。それに、作業で畑を踏み荒らされることは避けられなかったと思います。急斜面に竹を積み上げた足場も年を追う毎に弱く不安定になり、倒れた木を受け止める事ができなければ予想外の危険を生んでしまいます。なので、いずれにしても、自分で伐るしかなかったし、このタイミングしかなかったと今でも思っています。見守るしかない嫁は心配のあまり体調を崩してしまいました。
山間部にはこうして、誰も手をつけず放置された跡や、ゴミ、理に適っているのか疑いたくなる工事の穴が至る所にあり、何とも言えない気持ちになります。誰も正解を持ち合わせてはいないのではないでしょうか。
畑作りにおいて、陽当たりと風通しを確保できなければ、いくら土作りをしても、そこで身を立てることはできないのです。

 (写真上の昨年5月の状態、下から伐り進んできたところ)
(写真上の昨年5月の状態、下から伐り進んできたところ)