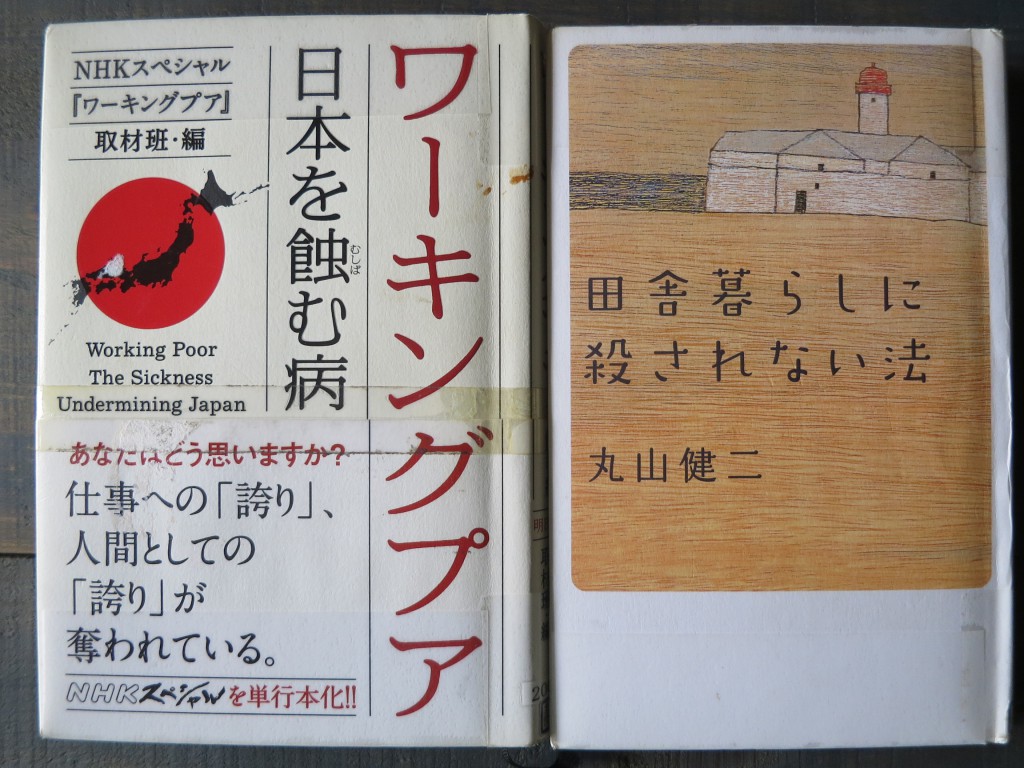10月10日未明、隣の空き家が火事になった。
大雨か雹か、何かがトタンを打つ激しい音に目を覚ました。次の瞬間、けたたましい足音とともに嫁が火事だと叫んだ。悲痛な声とはこのことか。胸にビリビリ裂けるような痛みが走る。障子越しからでも異変がわかった。裸足のまま庭に出るとあたりは真っ赤になっていた。激しい音を立てて炎が上がっていたのだ。何故これほどになるまで気付かなかったのか。誰も使っていないはずの隣家の納屋が火の中に骨組みだけを見せていた。もはや自分でどうこうできるものではない。何故そこが燃えているのか、思考が働かない。我が家とはほんの小道を挟んだすぐ隣だ。消防の番号を押そうにも緊張で目が霞む。ワンコールで繋がった。家々へ知らせに回った。皆寝静まっていた。喉が枯れて声が思うように出ない。指笛を鳴らし、何度も叫んだ。戻ると庭に火の粉が降っていた。粉ではない。熾の塊だ。冬枯れした芝生の方々で火が上がる。足で踏んで消して回った。とにかく少しでも火の勢いを弱めないと。火元へバケツで消しに行った。水場とを2、3回行ったり来たりしただけで、息が切れて喉がカラカラになった。腰が抜けそうだ。隣接する工房のプロパンガスのことを思い出してコックを閉めに行った。タンクが驚くほど熱くなっている。壁板も熱い。もう近づいたらいかんと声がした。
消防が来た。あと少し遅かったら工房も我が家も全て燃えていた。壁が燃え始めていること気づいた地元消防団の知人がこちら側に放水するよう指示してくれたのだ。じわじわ煙が上がっている板壁の一部から一瞬火が吹いた。それは、全面が燃え上がる前兆だった。
裏山の植林を伐り、まめに草を刈っておいてよかった。でなければ山火事にまでなっていただろう。隣家は納屋も母屋も全焼した。
数日経って、疲れがどっと出てきた。寝れないのだ。
新聞の報道に呆れた。火事の要因と考えられるモミガラ燻炭の不始末。離れを間借りしていた当人は過失を認め、事情聴取を受け、現場検証にも立ち合っていた。警察にも消防にも、そして周りにも誰かは伝わっていることなのに、新聞は何を勘違いしたのか、家を焼かれた貸主が燻炭作りをしていたと書いたのだ。しかし、翌日の朝刊に詫びも訂正という形も取られてはいなかった。誤解を解く内容ではあったが、前日の報道を詳しくしたという体であった。
社会とはそうしたものだと思うとやりきれない。今回の火事についても、責任を追及したいわけではないが、過失なところとそうでないところがある。籾殻燻炭による火事というのはよくあることとして知られており、消えたと思っても中で燻っているもの。なので、普通、納屋や小屋など建物にしまうものではない。そもそも、当人は貸主に断りもなくその納屋を使っていた。問いただしてみれば、危ないものとしての認識はあったという。しかし、ならば自分の目の届きやすい近くに置くべきところ、どういった了見で母屋を隔てた奥にある納屋に置いたのか。逆に我が家の目と鼻の先ではないか。実際、はじめに火事に気付いたのは私たちで、通報が少しでも遅れていたら間違いなく我が家は燃えていた。話してみても、その意味するところに考えが至らないようなのだ。幾度となく悪く捉えないようにしようとするものの、これまでもそうであったが、彼のその後の行いを見るにつけ、抱いてきた不信感は得体の知れない不安へと変わってゆく。土下座までして謝罪はするものの、こちらと向き合うことはしない。
あの償いの言葉は何だったのか。熱中症になりそうなほどの炎天下で焼け跡の片づけが連日行われ、兎にも角にも片付いた。ならば、言葉の通り、粛々と荷物をまとめるものと思っていた。が、一向にその様子はない。
償いきれないということ。それでも償うべきを償うためにこれまでの人生を諦める。そんなことなかなかできるものではない。といって、開き直って悪びれず、なかったことにする態度が更に相手を苦しめ不安を強いる、ということさえも知らぬ存ぜぬで通すというのか。
とにかく、我が家は無事だった。工房の壁が焼け、窓ガラスが割れ、他にもそれなりに被害を被ったが、修繕ですみそうだ。悪く考え出せばキリがないし、悪様に言えばそれは自分に返ってくる。自問自答を続けるうち、戦うべきは己のみというところに落ち着く。ところが、物事はそう簡単には終わらなかった。二次被害とはこういうことなのかと思わせる出来事がさらに続いた。火事そのものよりも質の悪い、傷を癒えなくさせるものだった。
何とか気持ちを切り替えようとするものの日常を取り戻せずにいたある日、新聞に後日談のような形で記者による投稿が掲載された。困惑する被害者家族から、その内容についてどう思うか問われた。被害を受けた当事者への取材は一切ないまま、火事を起こした彼の人物像を、都合のいい思い込みのまま一方的に擁護するものであった。
自らの過ちを誤魔化すため虚構に虚構を重ねる。相手に潜んでいるかもしれない狂気を怖れるあまり言葉を選ぶ。いろんな人の濃淡入り混じった恐れが堆積して物事の真相をぼかしてゆく。我が身可愛さに、なんなら、その中に美談を見つけてでも一件落着させたい周囲の同調圧力。
実情を知らない、自らの生活に関わりのない第三者ほど、寛容であることを押し付けてくる。失敗は誰にでもあると加害者に同情するあまり、被害者が置き去りにされ、逆に被害者が受け入れ難きを訴えようものなら、立場が逆転しかねない圧力。身の内を吐露し、誰かに同意を求める行為は、相手を吊し上げる加害行為になってしまうのだ。心情としては当然のはずが、黙って口をつぐむしかない。被害者をそういう状況へ更に追いやるものだった。まだ渦中にいるのに、もう済んだことにされる。許す許さないどころではない、負った傷は依然生々しく、夢にうなされ、ちょっとした物音に目が覚め、未だ眠れない夜もある。正直、もう忘れさせてほしいのに、「地域は温かくこれからも隣人であり続ける」と締め括られていた。
実際のところ、火事が過失である以上、追及されるべきでないのだろう。誰だって何かの間違いで起こしてしまうかもしれない。だから、事件性がある場合や、被害者が刑事告訴しない限り、その原因や責任の所在が明らかにされるものではないらしい。だから、突き詰めて言えば今回の場合、結局のところ火事の原因は不問ということになる。
そういった事情を知らなかった私は後日訪れた消防署員に原因は特定されたのか訊いた。邪推と受け取られても仕方がないが、当人のあまりの開き直り様、そして、実家を焼かれた人の心情や、これまで積み重ねてきたものを全て失い死ぬかもしれない思いをしたこちらの心情を顧みない傍若無人振りを目の当たりにするうち、ひょっとして、彼は、自分が原因ではないかもしれないという安易な処に落ち着こうとしているのではないか、という不安が頭をよぎり空恐ろしくなった。だから、確定したのかどうか気になったのだ。全ては誤魔化され、隣人であり続けるのが無理ならば、こちらが出て行くしかないというのか。被害者であることを振りかざすつもりはないが、しかしである。
消防署員の顔色が変わった。何故それほど気になるのか、当人との関係に何ぞ問題でもあったのか、問い返された。なるほど、火事の要因が籾殻燻炭であるには違いないが、発火原因は分からない。まあ、ないとは思うが、君がその発火原因と考えられないこともない、悪いことは言わないからこれ以上は立ち入らないようにと釘を刺されたのだ。
助言として受け取るべきなのか。しかし、まさか自分が疑われる可能性があるとは思ってもみなかった。第一通報者だから?彼を良く思わないというだけで?冤罪というものの恐ろしさ、堪え難さに初めて想い至った。かつてないほど精神の均衡を保つことに危機を感じた出来事であった。
人が違えば見え方は違うのだろうか。渦中にいると自分を見失いそうになる。幾度となく悪くとらえないように務めた。しかし、ついには面と向かって拒絶する必要があった。あろうことか、野焼きを始めたのだ。一日で終わらず、二日、三日と繰り返された。そして、空っ風吹くなか黒煙を上げ、異臭を上げ始めた。まだ周囲は気づいていないというのか。異常だと感じるのは私だけの主観でしかないというのか。ならばそれでもいい。偏った主観として、止めるよう断固として訴えるしかない。折しも、発泡スチロールの箱を燃え盛るドラム缶の中へ次から次へと投げ入れるところ、通気孔からは火が吹き出し、時すでに、近くに積まれた丸太に引火していた。にもかかわらず、当人は気付いていない。建物が隣接し、またもや手遅れになる所だった。しかし、それでも尚であった。また謝りはするものの、農作物の加工をするためと尚も食い下がる。これを機にようやく事は動き出した。こんな、つまらないことで、人生を台無しにされたくないという必死な思いだった。
考えないようにする。気にしないようにする。見ないようにする。いつか終わりが来ると信じて耐え忍ぶ。本当にそんなことが出来ただろうか。火事から半年が経とうとしていた。